|
セルフデクルは self-declaration の短縮カナ表記
|
|
消費税ソーシャルデザインGのブログはこちらです。 最近の掲載記事 全国のみな様への呼び掛け これからの消費税政策(消費税ゼロ決済)のあり方について 二重課税と決別する消費税ゼロ決済の提案 二重課税との決別 取引の原点に立返るー事例紹介 取引の原点に立返るー物価高騰を穏やかにする消費税ゼロ決済 二重課税との決別 - 消費税ゼロ決済の実現 取引で預かり税を無くして二重課税を解消 消費税0決済方式が売上を伸ばし経済社会を救う 消費税ゼロ社会の実現にむけて 事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現 外消費税の収奪を唆す総額表示方式は憲法30条違反 事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現 総務省発出の消費税に係る無効PDF文書 価格高騰を乗り越える家計に優しい取引額表示方式への転回 直接消費税を無くして物価高騰を乗り切る 消費税抜きで日々生活できない社会で国民が家計資産の目減りを食い止める「消費税の闇を破る光明」というのを共有し、国民的議論に発展させると逆転の発想で消費税をソーシャルデザインできます。 消費税の闇とは、取引おける総額表示方式が日本国憲法第30条の条規に反し、憲法第98条により総額表示に係る一切の行政行為が無効である事実を社会全体に認識がないことです。 消費税の闇を破る光明は、違憲の総額表示方式に代わるものとしてソーシャルデザインGが呼び掛けている「取引額表示/決済方式」であって、これは間接消費税込価格を消費者に表示し、その価格で決済するもので、価格に外消費税を加算しない元の間接消費税込価格で決済でき、家計資産が目減りすることはありません。 総額表示方式に係る違憲行為を差し止め「取引額表示/決済方式による取引」へと転換するのをコペルニクス的転回ということにすると、消費税をソーシャルデザインできます。 国の一般会計税収で消費税の税収が占める割合は凡そ30%であるように消費税に係る税収の根源は価格に含まれる「間接消費税」であり、「引額表示/決済方式による取引」が社会を支えています。 事業者は憲法違反の汚名を着ないためにも、価格表示又は請求する金額或いは料金に係る注記を「間接消費税込」に変えてコペルニクス的転回しなければなりません。 政府及び地方公共団体は総額表示に係る一切の行政行為を無効とする所要の措置を講じてコペルニクス的転回するべきです。 政府が違憲の総額表示義務の旗を降ろさないなか、地方公共団体を含む全ての企業・事業者は自らのWebサイトで取引の原則を「取引額表示/決済方式」とすることを宣言するだけでサイト閲覧者に総額表示方式と決別していることを認識して貰えます。 ご意見があれば何なりとお寄せください。iso@selfdecl.jp ここらで椅子から立ち上がり、スクワットを10回以上して下肢を鍛えるようにしましょう。 大切な眼の保護のため、画面を大きくして閲覧し、時々スマフォから離れるように心がけましょう。 続いて「消費税の闇を破る光明」をご覧ください。 それでは一旦休憩です。See You later 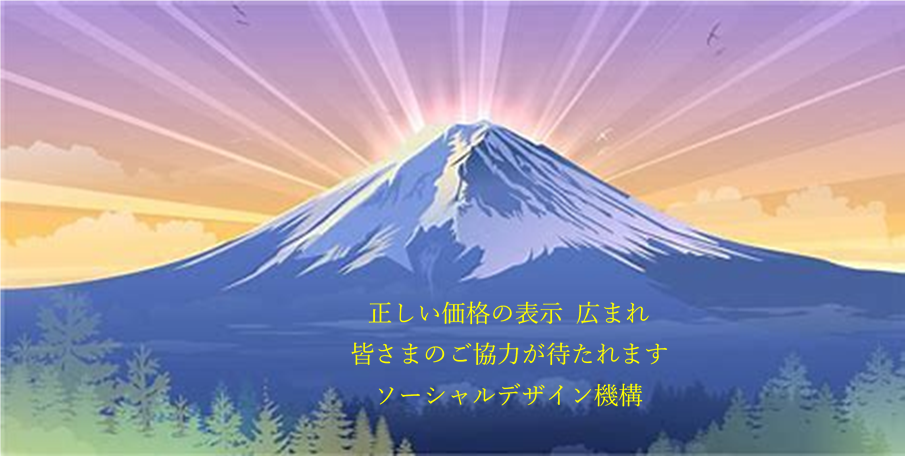
since 2001.06.08 ソーシャルデザインG iso@selfdecl.jp 代表 清水博 〒524-0011滋賀県守山市今市町139-4 上へ 取引の原点に立返るー事例紹介 消費税法第63条の条文 事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。 消費税法63条でいう消費税は、価格=「対価×(1+消費税率)」で表す価格に「間接消費税」として含まれる。 魚市場で寿司屋が鮮魚を500円でセリ落し、その鮮魚を鮨にして顧客に告げた1500円で提供した場合、上式により価格500円、1500円にはそれぞれ37円、111円の間接消費税が含まれている。 ここで、流通における通念になっている消費税は、譲渡価格=「価格(税込)×(1+消費税率)」で表す価格に上乗せするものであり、二重課税になる価格500円、1500円に対する消費税は請求すべきでない。 価格に消費税を上乗せする行為は日本国憲法第30条の条規に反する。 もう一つ例示すると、材木商から材木を100万円分仕入れた木工店が製作した200万円分の家具を家具店に卸し、台所用小物木製品50万円分をスーパーに卸した。 これら100万円、200万円、50万円は各事業者間の商談で決められた価格で、それらにそれぞれ9.01万円、18.18万円、4.54万円の間接消費税が含まれているので、各価格に対する上乗せ消費税の授受はない。 小物台所用木製品50万円分を仕入れたスーパーは木製品1個2万円で50個販売することにした。ちなみに1個2万円には1,818円の間接消費税を含むので、該木製品を1個2万円で販売しても法的問題はない。 しかし、スーパーは他の商品と同様に消費税率10%に設定したレジでバーコードの価格を読み取り、顧客は表示される請求額2.2万円を支払わざるえない。 小売業における違憲行為の常態化の原因は、政府が喧伝する総額表示価格=「価格(税込)×(1+消費税率)」で表す額での決済が習慣となっていることである。 この解消は決済端末のレジで消費税率を0%に設定することである。 間接消費税込価格に消費税を上乗せしないで取引するのを消費税ゼロ決済方式という。 小売事業者に商品が届くまでに複数の川上事業者が介在する。 あらゆる全ての事業者が譲渡価格に係る消費税率をゼロにする消費税ゼロ決済方式で事業者間取引すればそれぞれの事業者の決済額は税率分下がるので企業物価指数は下落し、消費者物価指数が上がることはなく、最近の物価高騰を回避できる。 調達などの入札金額に加算消費税を見積もるのは違憲行為であり、落札金額に上乗せ消費税を支払う必要はない。相手組織の財政負担を10%軽減できる。 政府は諸物価高騰を和らげる消費税ゼロ決済方式に賛同し、消費税の二重課税政策と決別する旨の談話を発表する。 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.09.18 上へ これからの消費税政策(消費税ゼロ決済)のあり方について ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp) 財務行政へのご意見・ご要望の受付:財務省 (mof.go.jp) 消費税法第63条で定義される価格「=課税標準となる対価の額×(1+消費税率)」が本来の税込価格である。 一方、現在の消費税率に至る過程で価格を「価格×(1+消費税率)」で表示させ、「価格×消費税率」を「消費税」と呼ぶようになった。 消費税率を0にしても消費税法第63条に規定による「価格の表示」に影響しないので事業者の期毎の納付税額の計算に影響はなく「社会保障の財源」について議論の必要はない。 無効である総額表示義務はさておき、二重課税解消の鍵は消費税を発生させないことであり、取引で支払い請求金額を計算する過程で売上に影響しない「消費税=価格×消費税率」をゼロにする決済を「消費税ゼロ決済」と呼ぶことにする。 「消費税ゼロ決済」の影響は、事業者が「消費税を収奪」できなくなることであるが、違憲行為を止めるチャンスと心得るべきである。 政府は法的根拠のない総額表示義務を喧伝し、事業者に二重課税になる消費税の収奪を煽っている。この行為は日本国憲法第30条の条規に反し、憲法第98条により無効である。 事業者は「消費税ゼロ決済」を取引の基本理念とし、「料金・代金等の請求・領収に当たり消費税を収奪しない」及び「取引の支払いに消費税を伴にしない」を実践すべきである。 小売事業者を含む全ての事業者が消費税ゼロ決済して二重課税から決別すると取引の当事者間で消費税の授受が無い社会が実現し、物価指数は下がる。 最近の物価高騰も消費税ゼロ決済で消費税が除去される額だけ和らぐ。 消費税ゼロ決済しない組織は、消費税経理の見直しなど「天網恢恢疎にして漏らさず」の結果が待っている。 20022.11.05 滋賀県守山市今市町139番4 清水博 上へ 全国のみな様 二重課税解消で消費者負担を0にする消費税ゼロ決済の提言です。 取引の計算機能の消費税0%設定で消費税を支払わずに生活ができます。 消費税率0%設定でも価格は変わりませんが、消費者は価格に含まれる間接消費税を負担します。 消費税法第63条により価格が決まると自ずと間接消費税が決まります。 この価格に消費税率を乗じると消費税が発生し、二重課税になります。 消費税を発生させない消費税ゼロ取引では二重課税になりません。 違憲行為である二重課税を無くすことを全国津々浦々に伝えるためhttp://www.selfdecl.jp/#zero1に「二重課税との決別」を公開しました。 社会保障の原資になる事業者の期毎の消費税納付額は、売上総額に係る消費税から仕入総額に係る消費税を控除した額ですが、二重課税でない消費税ゼロ取引でも、売上に含まれる間接消費税がコペルニクス的転回して社会保障費の財源は確保されます。 地方公共団体をはじめ多くの組織・団体は、総務省からの通知文書000269588.pdfや 000269591.pdfに対応する形で国の二重課税政策に加担し民間事業者に大きく影響を与えてきました。 自治体が二重課税から決別するコペルニクス的転回の一つに「料金等の徴収に当たり住民から消費税を収奪しない」があり、二つに「取引の支払いに消費税を伴にしない」があり、自治体の支出額の10%が節約でき、財政規律の改善に寄与します。 持続可能で健全な消費税の仕組みになるようコペルニクス的転回を実践する消費税ゼロ決済を提唱します。 ご理解頂ける事業者様は、この提言の啓発に協力いただき、また、自ら「消費税ゼロ決済」の取引を公表し、これを直ちに実践して下さるようお願い申し上げます。 2022.11.03 滋賀県守山市今市町139番地4 清水 博 81歳 上へ 二重課税と決別する消費税ゼロ決済の提案 消費税法第63条により価格が決まると自ずと間接消費税が決まります。 この価格に消費税率を乗じると消費税が発生し、二重課税になります。 二重に課税する売手が得し、買手が損する異常取引ですが、消費税ゼロ取引では当事者間で消費税の授受がないので二重課税になりません。 違憲行為である二重課税を無くすことをコペルニクス的転回と言うことにし、全国津々浦々に伝えるためhttp://www.selfdecl.jp/#zero1に「二重課税との決別-コペルニクス的転回」を公開しました。 社会保障の原資になる事業者の期毎の消費税納付額は、売上総額に係る消費税から仕入総額に係る消費税を控除した額ですが、二重課税でない消費税ゼロ取引でも、売上に含まれる間接消費税がコペルニクス的転回して社会保障費の財源は確保されます。 地方公共団体をはじめ多くの組織・団体は、総務省からの通知文書000269588.pdfや 000269591.pdfに対応する形で国の二重課税政策に加担し民間事業者に大きく影響を与えてきました。 自治体が二重課税から決別するコペルニクス的転回の一つに「料金等の徴収に当たり住民から消費税を収奪しない」があり、二つに「事業者との取引の支払いに消費税を伴にしない」があり、自治体の支出額の10%が節約でき、財政規律の改善に寄与します。 以上自治体をはじめ全ての事業者は、違憲行為を排除し財政規律改善のため、消費税を発生しない消費税ゼロでの決済を提言します。 2022.10.25 滋賀県守山市今市町139番地4 清水 博 81歳 上へ 二重課税との決別 消費税法第63条により価格が決まると自ずと間接消費税が決まります。 この価格に消費税率を乗じると消費税が発生し、二重課税になります。 二重に課税する売手が得し、買手が損する異常取引ですが、消費税ゼロ取引では当事者間で消費税の授受がないので二重課税になりません。 違憲行為である二重課税を無くすことを全国津々浦々に伝えるためこの「二重課税との決別」を公開しました。 社会保障の原資になる事業者の期毎の消費税納付額は、売上総額に係る消費税から仕入総額に係る消費税を控除した額ですが、二重課税でない消費税ゼロ取引でも、売上に含まれる間接消費税がコペルニクス的転回して社会保障費の財源は確保されます。 地方公共団体をはじめ多くの組織・団体は、総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で消費税の二重課税政策に加担し民間事業者に大きく影響を与えてきました。 政府は総額表示義務を振りかざし二重課税政策を定着させていますが、この二重課税政策が様々な要因で毀損した日本経済再生の足枷になっているところ、二重課税政策から消費税ゼロ政策へとコペルニクス的転回を図らなければなりません。 民間事業者の範となる地方公共団体が率先して「料金等の徴収に当たり住民から消費税を収奪しないこと、及び、事業者との取引の支払いに際し消費税を伴にしないこと」を実践し、これを出納・支払事務の要諦に定めておき、この実践の状況は住民(自治会)の監視を受けます。 このように地方公共団体は、政府が喧伝する総額表示義務や総務省からの上記通知文書の無効に気付き、前非を悔いてなすべきことを自覚して「二重課税政策と決別する旨を公表」し、実践しなければなりません。 元より法的根拠がない総額表示義務は無効であり、事業者が消費税ゼロで売上代金を収納すれば、消費税ゼロ社会が実現します。 事業者を利してきた経済再生の足枷である消費税25兆円/年を消費税ゼロ社会で有効に活用すればさしたる対策が無くても経済の好循環は確実に実現します。 この論理に懸念があるときはご連絡ください。 2022.10.23 滋賀県守山市今市町139番地4 清水 博 上へ 取引の原点に立返るー物価高騰を穏やかにする消費税ゼロ決済 内閣総理大臣 岸田文雄 殿 取引に消費税はつきものであり、価格、料金など譲渡金額が定まると消費税法第63条の規定により一義的に価格に消費税が含まれる。 事業者が表示する価格が法第63条の税込価格=「対価(税抜)×(1+消費税率)」であり、この価格で決済すると消費税は発生しない。 事業者が表示する総額表示価格が総額表示価格=「価格(間接消費税込)×(1+消費税率)」であり、この価格で決済すると消費者に消費税の二重負担を強いるが消費税率を0%にすると消費税は発生しない。 事業者が設置する代金・料金等取引額の請求端末(レジ、手動)ごとに設定変更(10%→0%、8%→0%、印字字句等)しておくと総額表示価格決済でも消費税は発生しない。 変更後のレシート出力の確認を終えておくものとし、消費税ゼロ決済後に発行する領収書には「消費税ゼロ決済」の字句を印字してもよく、インボイス制度を気にしなくてよい。 総額表示している事業者は、自らの裁量で誰にも妨げられず取扱品目の全部又は一部について何時からでも消費税率0%設定で「消費税ゼロ決済」できる。 総額表示決済と消費税ゼロ決済が併存してもドミノ的に後者に収束する。 社会全体が法第63の税込金額で取引・決済をすると個々の事業者の領収額が下がり、社会全体で物価が下がり、物価高騰を回避できる。 調達や入札はどの組織でも行われているが、入札金額や見積金額を法第63の税込金額にすれば相手組織の支払負担を10%軽減する。 政府は諸物価高騰を和らげる消費税ゼロ決済方式に賛同し、消費税の二重課税政策と決別する旨の談話を発表するとよい。 消費税ソーシャルデザインG滋賀 滋賀県守山市 清水 博 2022.09.20 上へ 二重課税との決別 - 消費税ゼロ決済の実現 内閣総理大臣 岸田文雄 殿 これまでの独壇場であった総額表示決済方式に代えて消費税ゼロ決済方式へとコペルニクス的転回に関するものである。 前者は表示価格に消費税を上乗せして決済するのに対して後者は表示価格で決済して消費者への請求金額を低く抑える。 消費税は医療・社会福祉に充てられるが、事業者ごとに売上総額に係る消費税から仕入総額に係る消費税を控除して算出した消費税を納付する。 消費税法第63条の規定により価格を決めると「対価×(1+消費税率)」のとおり消費税を含む価格になるので、消費税納付経理に必要な仕入に係る控除額を算出する。 事業者は法的根拠のない「総額表示義務」に誑かされ、代金・料金等の取引額の請求端末で消費税率8%/10%に設定した収奪行為により、消費者は消費税の二重負担に晒され、経済は毀損の一途を辿る。 事業者が設置する代金・料金等取引額の請求端末で消費税率を0%に設定することで消費税ゼロ決済を実現する。 消費税ゼロ決済後に発行する領収書には「消費税ゼロ決済」の字句を印字してもよく、インボイス制度の対象にならない。 コペルニクス的に転回する事業者はあらかじめ取引額の請求端末(レジ、手動、POSレジシステム)ごとに設定変更(10%→0%、8%→0%、印字字句等)し、変更後のレシート出力の確認を終えておくものとする。 料金請求に関わる事業者を含む原材料事業者から小売事業者に至るあらゆる事業者が消費税の収奪がない消費税ゼロ取引・決済をすると消費税の二重課税と決別でき、事業者の領収額が下がり、企業/消費者物価指数が消費税率分下がり、物価高騰の波が穏やかになり、住宅購入から大根一本でも消費税ゼロで購入できる。 二重課税と決別する事業者は、自らの裁量で取扱品目の全部又は一部について何時からでも消費税率を0%に設定し「消費税の収奪がない消費税ゼロ決済」にコペルニクス的転回を果たし、総額表示決済と消費税ゼロ決済が併存してもドミノ的に後者に収束する。 政府は諸物価高騰を和らげる消費税ゼロ決済方式に賛同し、消費税の二重課税政策と決別する旨の談話を発表する。 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.09.09 上へ 取引で預かり税を無くして二重課税を解消 消費税のカラクリを解明するため理解しておくべき消費税は二つあります。 一つは、消費税法第63条で定義される価格を決めると自ずと価格に含まれる間接消費税で、取引を通じて消費者が負担するもので社会保障費の原資です。 事業者が納税期間中の売上げに係る係る消費税から納税期間中の仕入れに係る消費税を控除した額の消費税を納付するので社会保障費は確保されます。 もう一つは、取引の支払いの時に価格×消費税率の額を事業者に収奪される外消費税で、この経理・使途は不明で、事業者がねこばばして関電事件など反社会的使途に流れているのを否定できず、「外消費税、預かり税や仮受消費税」を曲解して消費税と称して収奪するのは憲法第30条の違反行為です。 使途不明の外消費税は間接消費税込取引価格×消費税率であり、経済に様々な悪影響を及ぼす二重課税の元凶です。 原材料事業者から小売り事業者に至るあらゆる事業者は取引の度に法的根拠がないまま外消費税(預かり税)を発生させています。事業者が取引で外消費税の計上を止めれば二重課税から解放され、需要者が負担するのは価格に含まれる間接消費税だけになり総額表示方式と決別したことになります。 あらゆる事業者は外消費税を収奪するのは日本国憲法第30条の条規に反する行為であることを認識して、外消費税(預かり税)の計上を止め「価格を表示又は提示してその価格で決済する」取引方式を確認し、健全で持続可能な消費税に戻すべきです。 永い間政府及び政府の二重課税政策に加担してきた自治体及び公共料金収納事業者が日本国憲法第30条の条規に反する行為であることを認めるのかどうか、外消費税(預かり税)の計上を止めるかどうか関係者の議論を待つことになるでしょう。 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.08.07 上へ 消費税0決済方式が売上を伸ばし経済社会を救う 公平で持続可能な消費税の仕組みに蘇らせようと消費税ゼロ決済方式の啓発に取り組んでいる滋賀県守山市在住のソーシャルデザインGです。 知っているようで分かっていない消費税のこと、社会保障費の財源は消費税ですが、総額表示で発生する直接消費税ではなく価格に含まれる間接消費税です。 消費税法は間接税であり、事実上消費者に消費税を課す直接税になっていますが、日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規により消費者に消費税を課すのは違憲です。 法第63条で価格を決めると自ずと間接消費税が含まれるにも拘らず、取引では間接消費税込価格に直接消費税を上乗せするのが習慣になっています。 この二重課税が国民・経済を悩ませる元凶であり、これを解消するのが取引の当事者間で消費税の授受を行わない「消費税ゼロ決済方式」です。 最近の物価高騰が国民生活を脅かしている状況に鑑み、永く続いた総額表示方式と決別して、事業者が自主的に「消費税ゼロ決済方式(=間接消費税込価格表示/決済方式)」に転換すれば総額表示方式から脱却できます。 「消費税ゼロ決済方式(=間接消費税込価格表示/決済方式)」で取引する事業者は、法第63条の定義に従い「間接消費税込価格」を表示し、その価格で決済し、発行する領収書・レシートに消費税の字句を記載・印字すべきでなく、政府が導入を画策しているインボイス制度に煩わされません。 事業者が税務署に納付する消費税額の算出に際して控除する仕入に係る消費税額は、期間中の仕入れ総額から算出できます。 事業者は、「見積・請求」或いは「価格の表示」によってのみ「消費税ゼロ決済」を主張でき、外消費税を授受しないので売上を伸ばすことができ、燎原の火のように消費者物価は安定に向かいます。 「消費税ゼロ決済」の主張は総額表示義務との決別であり、小売取引にあっては商品ごとに付けるバーコードなどに外消費税を除去する税率0など決別のキーワードを潜ませるのが簡便です。 事業者間取引にあつては契約手続きの「見積・請求」ごとに消費税を含めないことで総額表示方式からの決別を主張できます。 政府が総額表示義務を喧伝するようになった経緯は、かつて「消費税率(国・地方) の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて」(平成 25 年 10 月 8 日付総財公第 103 号・総財務第 118 号)を、消費税率が8%に改定される旨のPDF文書を総務省から都道府県を経由して各地の地方公共団体等に通知したことです。 この法的根拠のない通知は無効であり、同様の総額表示義務に地方公共団体が同調しても総額表示の正当性はどこにもありません。 地方公共団体は地域における大口需要者であり、関係する供給者(事業者)との契約で供給者に消費税を収奪させ、また、関係する公共料金に係る消費税を収奪していますが、消費税の収支バランスから見ると財政破綻に突き進んでいます。 財政規律を考え「事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現」などの記事を参考に自治体の消費税に係る規定・取決め文言(例えばNHK放送受信規約第5条)を「消費税ゼロ決済方式」に整合させて総額表示方式からの脱却が不可欠です。 以上、地方公共団体を含むあらゆる事業者は違憲の総額表示に固執してきた前非を悔いて総額表示方式から脱却すべきであり、直ちに消費税ゼロ決済方式に転換すべきです。 消費税ソーシャルデザインG 080-5794-5324 滋賀県守山市 清水 博 2022.07.27 上へ 消費税ゼロ社会の実現に向けて 法的根拠がない総額表示方式により商品価格に加算される上乗せ消費税額を除去するのが総額表示方式と決別できるという論理により、消費税法63条に由来する取引額表示/決済の流れのなか決済レジで消費税率を0にして上乗せ消費税額を除去する消費税0取引システムを開発しました。 価格高騰が国民生活を脅かすようになっているところ、この消費税取引0システムが問題なく機能することを実証しておく必要があります。 価格に消費税を上乗せ加算するのは違憲行為であるので総額表示方式を決別し、公共料金等の請求額の算定根拠である料金(表)は間接消費税込価格でなければなりません。 対面取引事業者が使うレジで消費税0%に設定するだけで出力するレシートに「消費税に係る字句」の印字はなく、総額表示義務との決別を宣言したことになります。 消費税0が日本経済にとって欠かせない誠に稀有なことで、消費税0による総額表示義務との決別は事業者が自主的に決めるもので野火のように全国津々浦々の企業に広まっていくきっかけになるものと想定し、消費税を収奪している事業者や商店街の事業者をターゲットに消費税率を0に設定する事業者を募ることを考えています。 つきましてはhttp://www.selfdecl.jp/index.html#shutaiに掲げる【事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現】という記事を改めてご理解の上、消費税0取引システムにご意見を賜りたくご賢察のうえ何卒よろしくお願い申し上げます。 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.07.10 上へ 外消費税の収奪を唆す総額表示方式は憲法30条違反 政府は総額表示義務を喧伝しているが、日本国憲法第30条の条規に照らして、消費者は消費税の納税の義務を負っていない。 公共料金の支払いも総額表示方式で請求があり、料金請求額×消費税率で算出される直接消費税を収奪する。 これは違憲行為であり、憲法98条により無効であり、場合によっては政府は収奪した消費税の返還請求訴訟事件に対応しなければならない。 消費税の返還請求の額は最大で年間のGDP×消費税率になる途方もない額である。 政府は、法的根拠のない総額表示方式の無効を宣言し、事業者が主体の消費税ゼロ社会の実現を待たなければならい。http://www.selfdecl.jp/index.html#shutai 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.07.05 上へ 事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現 消費税率を変えるのではなく、法的裏付けのない総額表示義務を喧伝する政府にその旗を降ろさせ、価格高騰の波を制御する考え方に切換えれば健全で持続可能な消費税社会の展望は開けます。 さて、消費税法第63条に定義されているように譲渡価格を決めると自ずと間接消費税が含まれます。この間接消費税込譲渡価格(内税価格という。)を表示して内税価格だけで取引を決済し、当事者間で消費税を授受しないのが消費税0社会の根幹です。 ところが事業者は違憲の総額表示義務に従い消費税と称して直接消費税(=外税=内税価格×消費税率)を収奪させられています。 そこで、取引にあたり事業者に違憲行為である消費税(=取引額×消費税率)を収奪せずに決済額に加算する消費税0化システムを案出しました。 このシステムは消費税を0にすることで総額表示方式と決別する結果、仕入価格が下がります。 この消費税0化により直接消費税と決別しても内税価格に含まれる間接消費税を原資に所定の算式で算出される消費税は期末に税務署に納付されます。 総額表示方式から消費税0化システムへの切り替えは(レジで)直接消費税率0%に設定し、代金、料金の支払い請求額を「内税込価格+(内税込価格×消費税率)」に変更するだけであり、領収書(レシート)に反映します。 なお、消費税0化システムの定着を促すため、上記直接消費税率0%の設定から一年間は支払い請求額を「内税込価格+(内税込価格×消費税率)」に変更しなくてもよいものとします。 領収書やレシートに反映させる事項は、①直接消費税は0であることであり、必要に応じて②売上額に係数0.0909又は0.0741を乗じて算出する間接消費税に言及することができます。 なお、決済額への加算分(内税込価格×消費税率)がある場合は消費税特別勘定科目に累積保存し、別途価格改定時に累積保存分で価格の上昇を穏やかにします。 ただし、事業者は価格を表示又は請求額を請求するときは内税価格で表すものとし、公共料金・通販料金などの請求額算定の基礎となる料金表を内税価格で記載しなければなりません。 請求額算定の基礎となる料金表を内税価格にすることが総額表示方式からの決別になります。 この論理で消費税0社会へと一歩前進するのが期待されます。 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.07.03 上へ 「消費税の闇を破る光明」-総額表示を止めて消費活動を活発にする 消費税の真実を知らなければ違法な総額表示価格に加え物価高騰の煽りを受けて生産者・消費者は右往左往しなければなりません。 消費税は、消費税法第63条で定義されており(課税標準となる資産や役務の対価)×(1+消費税率)で表される取引表示価格に含まれる対価×消費税の額で、間接消費税です。 一方で、政府が喧伝している総額表示方式は取引表示価格に消費税を課す二重課税になっています。 消費税は間接税であるにも関わらず、事業者間取引では見積請求で外消費税額が計上され、消費者との取引では事業者に日本国憲法第30条の条規に反する「総額表示義務」が課され、いずれも取引の当事者間で外消費税を授受する二重課税になっており、消費活動に影を落としています。 憲法第98条により無効である総額表示をやめて、消費税法第63条で定義される間接消費税込価格で取引すれば外消費税の授受は無くなり、代わりに物価が多少上がっても、消費活動は停滞することはありません。 違憲の総額表示方式により発生する外消費税分を物価の値上がり分で相殺し、取引額【(課税標準である対価+物価上昇分吸収額)×(1+消費税率)】を消費者に値札等で表示し、或いは見積請求で仕入先業者に提示し、その額で決済する「取引額表示/決済方式」を適用すると消費活動は活性化します。 法的妨げは無く何時からでも何にでも「取引額表示/決済方式」は個人事業者や公共料金請求事業者などを含むあらゆる供給者に適用でき、取引額表示の呼び方は、間接消費税を含む内税価格、表示価格、本体価格、料金、代金、請求額など様々です。 川上事業者も「取引額表示/決済方式」というコペルニクス的転回では電気、ガス、水道、燃料、などのライフラインや原材料、資材等の譲渡額に外消費税を加算せずに原材料等の値上がり分を譲渡額(取引額)に反映させれば川下事業者の仕入額が低くなり結果として消費者物価も低くなります。 コペルニクス的転換は、取引額には「間接消費税」が含まれていることを需要者に知らせるだけであり、商品ごと、売り場ごと、店舗ごとなどに適用でき、決済後に発行する領収書にその旨を明記できます。 さて、「総額表示方式」から「取引額表示/決済方式」へのコペルニクス的転回で事業者・消費者にどれだけの恩恵があるのか税込価格250円の場合を試算します。 税込価格を250円とした場合その外消費税抜価格=250÷(1+消費税率)=227.27円であり、間接消費税抜対価=227.27÷(1+消費税率)=206.61円です。 この対価206.61円に10%値上分を吸収させると227.27円であり、取引額=227.27×(1+消費税率)=250円です。 言い換えると、税込価格表示250円の商品の決済額は、「取引額表示/決済方式」では227.27円、外消費税分に代えて10%値上分を吸収させた場合は250円です。 これがコペルニクス的転回で、全ての事業者・消費者にとって消費税の闇を破る光明です。 ソーシャルデザインGセルフデクル 2022.05.20 滋賀県守山市 清水博 上へ 直接消費税を無くして物価高騰を乗り切る これまでの消費税政策は、真正の間接消費税政策がありながら消費税転嫁対策の名のもとに直接消費税を川下事業者に付け回しするものでした。 取引の総額表示方式に踊らされ日本国憲法第30条の条規に反する直接消費税の収奪を黙認・容認してきたのは私たち国民です。 取引額表示方式で事業者間取引して直接消費税が無くなると企業物価指数が消費税率分下がり、消費者物価指数も下がります。 取引額表示 = 消費税法第63条でいう間接消費税込価格 ¬=対価の額(1+消費税率) 真正の消費税は消費税法第63条で定義される間接消費税であるので、直接消費税が無くても国の消費税収に影響しません。 取引額表示では直接消費税の請求はないので表示価格で決済できます。 直接消費税が無ければ物価高騰を乗り切れます。 取引表示額に対価の額×値上げ率を加算するのです。 取引額表示 = 元の税込取引表示額+対価の額×値上げ率 試算:総額表示方式で支払総額11,000円であるものが「取引額表示方式」では支払額が10,000円であり、対価の額9090円×値上げ率10%=909円を加算しても10,909円で決済できます。 もとより総額表示義務の政策は憲法第98条により無効であるので、政府として無効宣言し、旧来の消費税転嫁対策は誤りであると認めるよう提言します。 消費税ソーシャルデザインG 滋賀県守山市 清水 博 2022.06.04 上へ 価格高騰を乗り越える家計に優しい取引額表示方式への転回 岸田文男 内閣総理大臣殿 取引額表示とは普段消費者が目にする「本体価格」のことで、本体価格で支払いを済ませば消費税分だけ家計消費額を減額できます。 取引額(本体価格)表示方式とは、消費税法第63条で定義される間接消費税込を表示し、表示額をそのまま請求額とする方式で、決済時の直接消費税の請求はないので事業者は業績を伸ばせます。 真正の消費税は消費税法第63条で定義される間接消費税であるので、直接消費税が無くても国の消費税収に影響しません。 事業者が総額額表示方式から取引額表示方式の料金表、代金、価格、料金などに変更する手順は以下のとおりで、面倒はありません。 ① 総額額表示方式にある(税込)などの注記を(間接消費税込)に変更し、消費税の字句を間接消費税に変更する ② 総額額表示方式の表示数値を消費税率で除した値に変更する 総額表示方式で取引するのが大勢を占める中、取引額表示方式適用の看板を掲げるのに躊躇する店には特典を設けることができます。 その特典とは、総額表示方式で事業者が収奪している直接消費税を価格に加算するのではなく価格に転嫁する形で物価上昇分を相殺するのです。 (詳しくは勉強会などで解説します。) 財布に優しい取引額表示方式へのコペルニクス的転回は必須で、物価高騰の折から国の指導が期待されるところ、消費税政策・経済対策を見直し、政権党ならではの然るべき措置を講じることを提言します。 なお、消費税転嫁対策の見直しが行われない場合は、地方政府が自ら行ってきた総額表示に係る不法行為を無効とし、取引額表示方式の適用を宣言させるのでご承知おきください。 消費税ソーシャルデザインG 08057945324 滋賀県守山市 清水 博 2022.06.08 上へ 総務省発出の消費税に係る無効PDF文書 https://www.soumu.go.jp/main_content/000269588.pdf「消費税率(国・地方) の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて」(平成 25 年 10 月 8 日付総財公第 103 号・総財務第 118 号)及びhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000269591.pdf「消費税率(国・地方)の引上げとこれに伴う対応について」(平成 25 年 12 月 24 日付総財公第 124 号 総財務第 158 号 )を、消費税率が8%に改定される旨のPDF文書を総務省から都道府県を経由して各地の地方公共団体等に通知しています。 その要旨は、各自治体に歳入面(公共料金に係る直接消費税)について、消費税の円滑かつ適切な 転嫁を基本として対処し、予算編成にあたり、歳出予算についても、その影響額(自治体の事業費や庁費の支出に係る直接消費税)について適切に 計上されるようにお願いするものでした。 上へ |